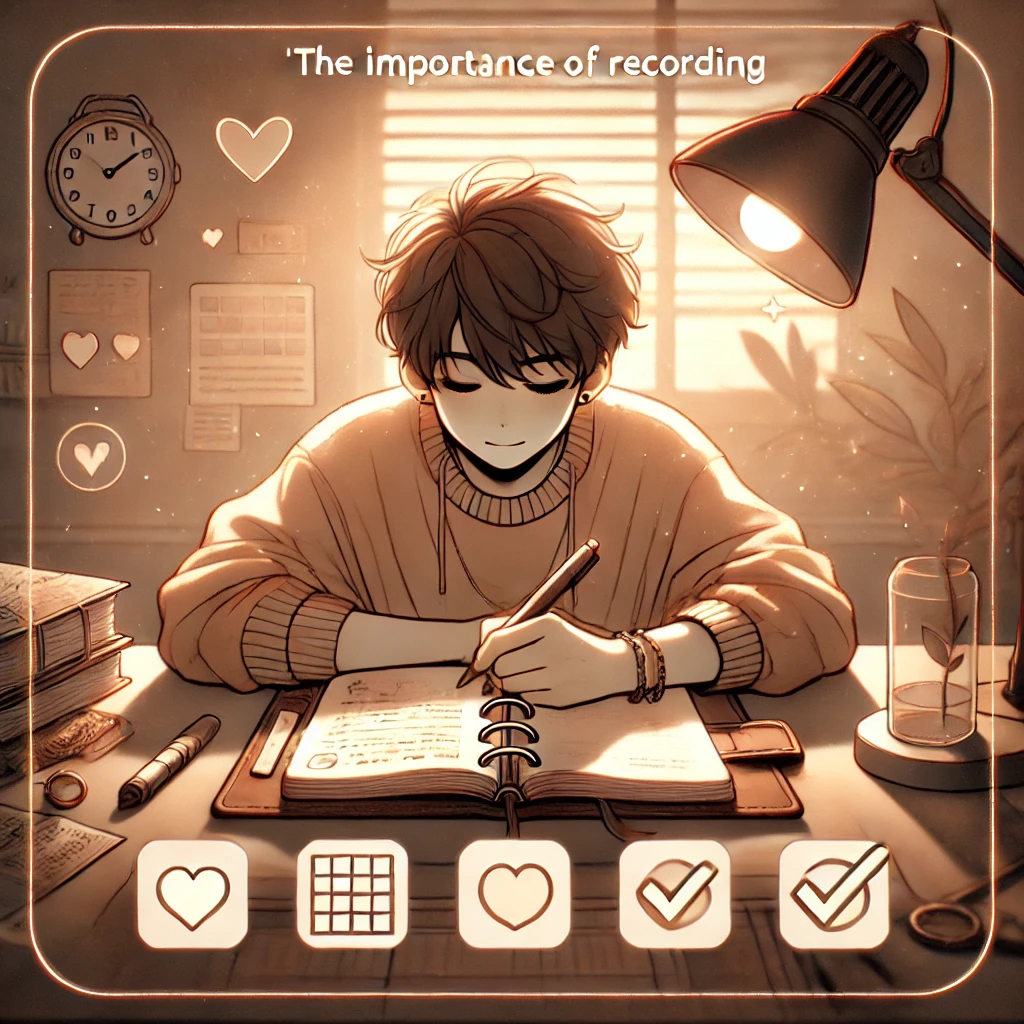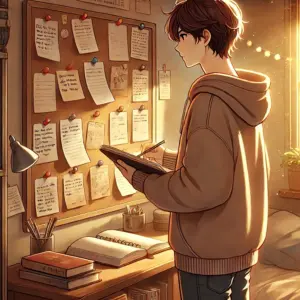パチンコ・スロットを「やめようと思ってたのに、またやってしまった」その理由
「今日は行かないって決めてたのに…」
「また使いすぎてしまった…」
「予定を変えてきてしまった…」
そんな経験、ありませんか?
“やめたい気持ち”があるのに、行動がついてこない──
それは意志が弱いせいではありません。
無意識に組み込まれた“クセ”が、いつもの通りに作動しているだけかもしれません。
この記事では15年ギャンブル依存症だった私自身が実際にパチンコ・スロットから抜け出した方法をわかりやすく解説しています。
同じように悩んでいるあなたのギャンブル脱出の手助けになれたら嬉しいです。
- 自分のクセを把握する“記録”方法
- なぜ“記録”が効果的なのか
- 我慢ではなくまずは記録がやめる近道
STEP確認
この記事はギャンブル依存症から抜け出すための「STEP1-1」です。
シリーズの他の「STEP 1」記事もあわせて参考にしてみてください。
- STEP 1-1【依存行動:まずやるべきことは“記録する”】 ←今ココ
- STEP 1-2【パチンコ・スロット依存衝動の“4つのトリガー”】
- STEP 1-3【パチンコ・スロット依存行動の“スイッチ”】
- STEP 1-4【パチンコ・スロット依存の回路を止める】
- STEP 1-5【“やめる準備”の土台作り】
シリーズ全体の流れを確認したい方はこちら。
【結論】まずやるべきことは“記録する”
まずやるべきことは“記録する”ことで、あなたの「クセ」を記録で見える化することになります。
例えば、こんな場面でギャンブルに行きたくなることがあります。
- 仕事でイライラした
- 家でひとりで退屈だった
- ATMでお金をおろしたついでに、「なんとなく」パチンコ屋の前を通った
これはもう少し分析すると「感情」と「きっかけ」が重なったときと言えます。
- イライラ+ストレス発散したい=ギャンブルを選ぶ
- 退屈+暇つぶししたい=ギャンブルを選ぶ
- お金に余裕がある+時間もある=ギャンブルを選ぶ
こうした感情と状況が引き金になり、脳が自動的に反応してギャンブル衝動に繋がっている。
これがあなたの「クセ」(傾向・パターン)で、流れとしては下記になります。
トリガー(1個以上) → スイッチON → 脳が自動で快感を欲求 → ギャンブル衝動!!
今回の記事ではまず記録について解説していきます。トリガーとスイッチについては次回の記事で解説していきます。
 保全士:ひろのぶ
保全士:ひろのぶ記録するって、機械でいえば「データロガー」(情報を自動で記録する装置)みたいなものです。
エラー履歴がわからなければ、どの部品が壊れたかもわからない。
人の感情も動きも、記録しなきゃ“原因”なんて見えてこないんですよね。
【効果】記録と見える化の効果
この「クセ」に対して“記録”で見える化することで下記効果が得られます。
- 「クセ」を把握することができる
- 「クセ」を抑える効果がある
- 見える化することで次のステップ、「クセ」への対応に進むことができる
次に記録が必要な理由を順番に解説していきます。
【理由①】脳の“報酬回路”は、意志より早く動く
なぜ記録して見える化することが有効か、それは私たちの脳は意思より早く動くためです。
ギャンブルで当たったときの快感。その記憶は脳の報酬系(ドーパミン回路)にしっかり刻まれています。
たとえば・・・
- イライラしているとき
- スマホでホールの広告を見たとき
- 給料日でお金に余裕があるとき
こうした場面で、脳は過去の快感を呼び出し、「またあれを味わいたい」と無意識に命令を出します。
【理由②】無意識に思考や行動をする
人間は慣れた行動を、考えずに自動でやってしまうようにできています。
これを「自動思考」や「習慣化」といい無意識で思考や行動をしてしまいます。
たとえば…
- 暇になったらスマホを見る
- 帰り道でいつものコンビニに寄る
- ストレスがたまると甘いものを食べる
ギャンブルもこれと同じです。
「感情」と「きっかけ」が重なったときがあると、無意識に脳が“ギャンブル”を選んでしまう流れができています。
【理由③】記録による“見える化”の力
ここで効果的なのが、記録による見える化です。
ただ記録するだけで、無意識の自動運転状態から意識して「自分で選べる状態」へと徐々に変わっていきます。
記録は具体的には
- やりたくなった状況をメモする
- 感情を言葉にして書き出す(例:「ストレス」「退屈」「孤独」など)
- どんな出来事がスイッチになったかを記録する
このようなアウトプットをすることで衝動をコントロールしやすくなります。
次に記録による効果を順番に解説していきます。



機械でいうと記録をすることで自分でメンテナンスのタイミングを選ぶことができます。もし記録しなければ機械が壊れるまで自動運転させることになってしまいます。
【効果①】記録しようとする行為がブレーキになる
たとえば記録をしようとした瞬間「なんで今、自分はこれをやろうとしてるんだっけ?」と、
一度自分の考えを“意識”することになります。
このとき無意識から意識に切り替わることで、必然的に理性が戻ってきます。
この時に働いているのが、脳の司令塔「前頭前野(ぜんとうぜんや)」で、
これは簡単に言うとブレーキの役目があります。
ですのでアウトプットをすることで衝動をコントロールしやすくなります。
【効果②】言語化によって“感情の暴走”が弱まる
感情が高ぶっているとき(イライラ・不安・モヤモヤ)ほど、私たちはその感情に引っ張られて行動しやすくなります。
ですが、感情を言葉にして記録することで、無意識の自動運転状態から
脳が意識的に自分を見つめる状態に切り替わります。
たとえば…
- 「今日は仕事で怒られてムシャクシャしていた」
- 「今日は友人に無視されて、すごく寂しかった」
- 「家で一人で過ごしていて、何もすることがなくて退屈だった」
と書くことで「あ、自分は今、怒りや悲しみ、退屈をギャンブルで処理しようとしてたんだ」と知ることができます。
これは自分がなぜギャンブルに行こうとしたのかを気付けるきっかけにできます。
また自分で自分にツッコミを入れるようなもので、ブレーキの役目にもなります。
【効果③】“反応”から“選択”に変わる
記録を続けると、自分の行動や感情に「クセ」があることに気づき始めます。
たとえば…
- 月曜は仕事帰りに行きたくなりやすい
- 雨の日は気分が落ちて、行きたくなる
- 給料日後は財布がゆるくなる
これに気づけた瞬間から、「反応」だけではなく「選択」をすることができるようになってきます。
このような効果がある為、記録による見える化という形でアウトプットをすることで衝動をコントロールしやすくなります。



機械も一緒で記録することでブレーキ、つまり過剰に運転させないように制御ができます。機械が故障という反応をする前に、メンテナンスをする選択を取れるようになります。
こんな人に特に効果的です
- 「何となくやってしまう」人
- 「気持ちの波と行動の関係」がわからない人
- 「どうしてまた行ってしまったのか」が整理できない人



頑張って直したいと思っても、原因が分かっていないと暴れる機械を無理矢理押さえつけて暴走しないようしているようなもの!我慢するくらいしかできないよ!
【補足説明】各種効果スキルのまとめ
ラベリング効果
感情を言葉にすることは心理学では「ラベリング効果(言語化によって感情が弱まる)」として知られており、その気持ちを弱めることができることが分かっています。
また脳科学的にも、脳の司令塔「前頭前野(ぜんとうぜんや)」と呼ばれる理性的判断を担う部位が活性化することで、ブレーキの役目があり、衝動をコントロールしやすくなるとされています。
メタ認知能力の向上
記録をして客観的に自分を見る、つまり他人から見た自分を知ることができます。
これは「メタ認知」と呼ばれ、自分自身の思考や感情を客観的に捉える能力のことを指します。
この能力が向上すればするほど現実的で冷静な判断ができるようになります
認知行動療法の1つ
この記録という行為は認知行動療法と呼ばれる考えと現実にズレがある状態に気づいて修正していく方法の1つで、医療機関や自助グループでも認知行動療法を行っています。
ギャンブル依存症の回復以外でも人生で役立つスキルの1つと言われるほど効果的です。
【実施】まずやるべきことは、“記録する”だけでOK
記録を始めるために必要なことは下記になります。
- いつ(日時)
- どんな気持ちだったか(感情)
- 何がきっかけだったか(状況)
- ギャンブルに行ったか、行きたくなったか(行動)
これをメモに残すだけで、自分の中にある“クセが見える化”していきます。
またアウトプットをすることで衝動をコントロールしやすくなります。
記録例:こんなふうに書けばOK
| 日時 | 状況 | 感情 | 行動 |
|---|---|---|---|
| 4/20(金) 18:30 | 仕事でミスして上司に叱られた | 不安、モヤモヤ | 駅前のホールへ寄りたくなって、行った。 |
| 4/22(月) 11:00 | 平日休み、家でひとり時間を持て余していた | 退屈、孤独感 | なんとなくスロットのデータを調べていた。その後行った。 |
| 4/23(火) 20:15 | 残業でストレスがたまった | イライラ、発散したい | いきたいけど時間が遅いのでそのまま帰った |
| 4/24(水) 19:00 | 友人のSNS投稿を見て「自分は何してるんだろう」と落ち込んだ | 焦燥感、自己否定 | 気分転換にホールへ行き、結果1万円負けた |
| 4/25(木) 17:30 | コンビニATMでお金を下ろしたついでに | 無意識、なんとなく | 店の前を通り、そのまま入店してしまった |
| 4/26(金) 18:00 | 仕事終わり、疲れてボーッとしていた | 無気力、ストレス | 「ちょっとだけ」のつもりで行って深追いした |
| 4/27(土) 11:00 | 朝からやることがなく、何をしようと考えた | 暇、期待 | 「今日は勝てるかも」と思って出かけてしまった |
→ ポイントは「行きたくなったときの気持ちときっかけ」を記録すること。



記録してみると、意外と“クセ”が見えてきます。
例えば、毎週月曜日や特定の時間帯に行きたくなるなど、自分の行動パターンが見えるはずです。
機械でも、「同じ時間帯」「同じ作業後」に異常が出やすい…なんてことはよくある話です。
これを知ることが、依存症回復に繋がります。
【まとめ】自分の「クセ」を見付ける
ギャンブルをやめる為に頑張ろうと少しでも思ったら我慢することではなく、自分を知って仕組みを作ることに労力を割くことが正しい頑張りだと私は考えています。
例えるなら勉強を頑張るといって夜中まで休憩無しで効率悪く頑張って勉強するのではなく、体調や栄養補給も万全にして集中できる環境を作る仕組み作りをして、後は仕組み通りにやる。
頑張ったけど駄目だったとなる可能性を減らす努力をする方が楽だし結果も出ます。



まぁぶっちゃけ「めんどくさい…」って思うかもしれませんが、出来るだけ読み進めてもらうだけでスムーズに行えるように記事を書いていきますので一緒に頑張りましょう!
- 「とにかく記録して見える化する」ことが最初の一歩。
- 記録するだけでブレーキになる
- 見える化は次の対策に繋がる
- 記録はスキルの1つ
次回(STEP1-2)
次は、「行きたくなるきっかけ=トリガー」について解説します。
- STEP 1-2【パチンコ・スロット依存衝動の“4つのトリガー”】
- STEP 1-3【パチンコ・スロット依存行動の“スイッチ”】
- STEP 1-4【パチンコ・スロット依存の回路を止める】
- STEP 1-5【“やめる準備”の土台作り】
関連記事
- STEP 0-1【パチンコ・スロット依存脱出ガイド】\まずはここから!/
- STEP 1-1【依存行動:まずやるべきことは“記録する”】 ←今ココ
- STEP 1-2【パチンコ・スロット依存衝動の“4つのトリガー”】
- STEP 1-3【パチンコ・スロット依存行動の“スイッチ”】
- STEP 1-4【パチンコ・スロット依存の回路を止める】
- STEP 1-5【“やめる準備”の土台作り】
このサイトが大切にしていること
「この世界は、生きづらいものだ」と思っていた過去があります。
でも今は、そう感じていたのは“思考の仕組み”が乱れていただけだったんだと気づきました。
このサイト「脱出思考」では、機械保全士として培った現実重視の“整備の視点”をベースに、脳科学や心理学の知識、そして僕自身の体験をもとに、思考や感情を“仕組み”として捉えるヒントをお届けしています。
よければ他の記事も覗いてみてくださいね。
参考・出典
- 厚生労働省,依存症についてもっと知りたい方へ,2025/4/21
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000149274.html - 厚生労働省,依存症対策,2025/4/21
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000070789.html